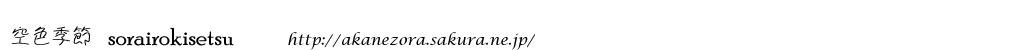
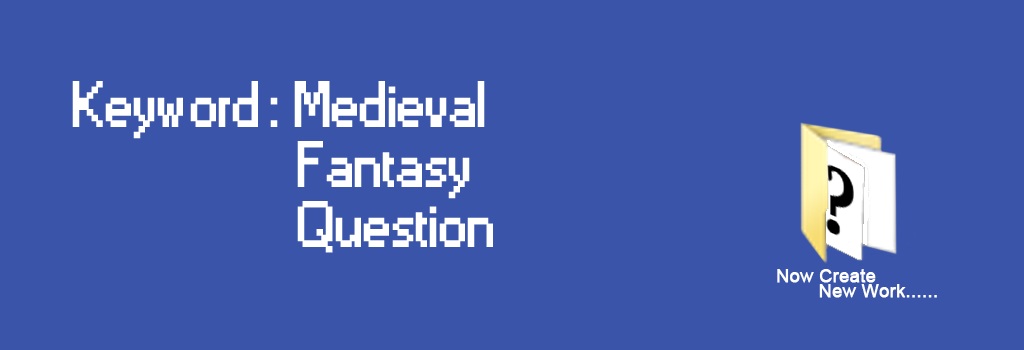

碧色のイヤリングを手の平で転がした。
一人で居る部屋、照明の光を目に返して輝いたそれを、夏樹は懐かしげに眺めている。大きさは小指の先程度しか無く、恐らく買ったとしても大して高価なわけでもなく、でも余り見かけない色合いをしたイヤリングだった。
思い出の品だと一目で気がつく夏樹の雰囲気、口元はうっすらと笑みが零れている。まるで過去を思い出すようにイヤリングに語りかけその先にある何かを見つめるような顔。
一度は肩まで伸びた髪をばっさりと切り、今ではうなじも見える位の長さで邪魔にならない程度に切り揃えられている。顔にはまだ幼さが残る顔で、これでも二十歳なのかと問えば夏樹は少しむくれたように言葉を返すのをよく見る。
座るベンチの隣にはぼろぼろになったシューズが置かれており、使い込まれ摩耗しくたびれたそれは今では使っていない。それでも夏樹は今日、この場所に持ってきたのだ。その隣には、青地に縁が白のリボン。少しだけ汚れているのが印象に残る。
夏樹の親友であり心が許せる工藤絵莉は、これを持ってきている理由を知っている。だからこそ、これを手にこの場所へ向かっている時は苦笑半分笑顔半分で言葉を掛けてくれた。
「まだ持っていたんだ」
捨てる気になれなかっただけだと言葉で返すと「はいはい」と夏樹をあやすようにして言葉を返した絵莉は、続けて「あなたらしいよ」と言葉にした。そして、「リボン…か」とだけ付け加える。そのリボンに込められた想いを知っている二人だからこそ、その言葉だけで伝わる。
夏樹が振り返る記憶は、別に楽しいことばかりではなく、辛いことや悲しいことももちろん有る。死にたい、居なくなりたいと感じたことだった一度や二度ではない。そんな感情を全て混ぜ込んで今は昔を思い返して口元に笑みが浮かぶのだ。
イヤリングから目を外した夏樹は、いつもの癖で右膝を揉んでは何度かペチペチと平手で軽く叩く。乾いた音だけで別段変わった痛みもない事を確認した夏樹が苦笑した。
「もしかして、不安なの?」
他に誰も居ない部屋だ。つまりその言葉は夏樹自身に向けられた言葉になる。
「まだ引きずる、かな?」
思えばこの一件が有ったから、ここまで来れたんじゃないか…と考えて、元々これが有ったから遠回りをした感じも有る。
「卵が先か、ひよこが先か…てねっ」
小さく笑う夏樹の肩が揺れる。合わせて手に載せたイヤリングが小刻みに揺れると、反射した照明の光、碧い光が目に飛び込んでくる―――――――――
「高宮夏樹です。よろしく」
抜けるような青さを持つ空だった。夏樹の簡単な自己紹介は、そんな空を尻目にするような感じを受けるだろう。季節外れの転校生、そんな第一印象と今の挨拶で夏樹への距離感を計り損ねているのは何も生徒だけではなかった。
新しい高校の制服は前の高校みたいに長いスカートではなく、膝上丈で裾付近に白い一本線が映えるスカート。上はワイシャツに指定のネクタイを着ける。一般的な女子の格好だが、夏樹が他の女子と大きく違う点があった。
「高宮さんは見ての通り怪我をしています。まだ慣れていない校舎でもあるので、助けてあげるようにしてください」
右膝に巻かれている痛々しい包帯。固定具をつけているため左足の細さに対してとても太く見える。そして身長一五二センチメートルを支える二本の松葉杖。
夏樹は教室に入った時から、この二点に視線が集中していることを痛い程に感じ取っている。どう見ても訳有りの転校としか言い様が無い訳だ。
記録会まで、後三日。それ次第で今年のインターハイへの切符が掛かるとなれば、自然と力が入る。そして夏樹だってもちろん例外ではなく、練習は通常よりも多く、そしてきつくしていた。
「おーい、夏樹。あんまり無茶しない方が良いよ」
絵莉の困り顔を横目にタオルで顔の汗を拭いた。
「あと、百メートルを三本やったらね。絵莉、悪いけどまたタイムやってくれないかな?」
「だから、やり過ぎだよ。他の部員はもうクールダウンしているよ。ねぇ、部長もなんか言ってよ!」
腰と膝を軽く柔軟してもう一度スタートラインの方へと歩いていく夏樹に、手を焼いている絵莉が部長にヘルプコールを出した。部長も苦笑一つで首をすくめると、絵莉が大きく溜息を吐いて、夏樹とは逆側、ゴールラインの脇に歩いていく。
「あと三本だけだよ。それ以上は絶対にダメだからね!」
「うーん、おっけー」
部長が手を挙げると、夏樹がスタートラインで走る体勢へと変わったのを見て、絵莉もタイムウォッチのボタンに指をかけた。
「位置について、よーい……スタート!」
バッと手が下ろされたのを合図に、ボタンが押され、夏樹は弾かれたように前へと進み始めた。
右足が土へとしっかり噛み、その反動を使って左足を前に出し土をしっかりと噛む。そして同様に右、左と交互に繰り返していく間に一気にトップスピードまで加速した夏樹。
見慣れている絵莉ですら未だにこの早さには驚かされる。むろん高校から一緒になった部員達からすれば未知の領域とも言える速度なのだから。
風を切って一歩前の光景は瞬時で後へ流れ、目の前には新しい景色が見えていく。
夏樹の得意分野の短距離では、部内では誰一人として勝つことが出来ない。いや、恐らく全国の同年代でも勝つことは不可能とも言える。
「神速……」
クールダウンしながら夏樹の走りを見ていた部員の誰かがそう口にした単語。たかが高校一年生の女子につけるあだ名にしては随分と大それた名前だった。だが、入部したてならいざ知らず、今ではその名前にけちをつける人も馬鹿にする人も居ない。
当の本人は特にそれらを意にかけないで己の走りのみを追求していく。更に早く、もっと先へと、それだけを考えて。
そしてゴールラインを切った時にタイムウォッチのボタンを押した絵莉、そして出されているタイムを声に出した。
「んっと、十一秒五、だね」
「えー…ベストじゃないかぁ」