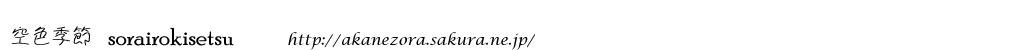
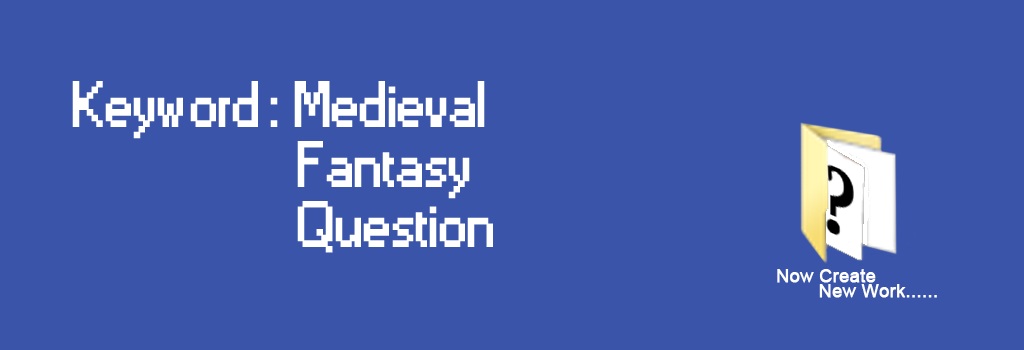

昨日の夜に降った雪は、路面を見えなくし白く染め上げている。歩く度に雪を踏む音が耳に届き、時折霜の柱が折れるような音がする。要するに雪の下は凍っていると言うことだ。
「思ったよりも降っていたんだね」
「まあ、まだ少し降っているからな。朝からだと考えると除雪してもこの程度かって思えるな」
まだ店が開くか否か位の時間帯、朝一番の除雪後だと考えるとこんなものだろう。およそ二、三センチメートル位か。靴底が雪を踏む度に見えなくなる位には積もっている道を並んで歩く。
「思えば、ここ最近、ずっと家の中で話をしているだけだったな」
「そう…だね。こうして外に行くのは久々かもね」
別に外へ行って遊ぼうと思わなかった。ただ茜と一緒に昔話をしたり、馬鹿みたいな掛け合いの会話をしたりするのが面白かった。満足しているのは確かなんだから。
茜は口元が隠れる位までマフラーを巻いており、長年愛用のマフラーとは違った物を使っている。
「あれ、前と違う柄か?」
「ん。ちょっと前に買い換えたんだ」
暗めの赤地に白と茶によるチェック柄。明るい色がクロスした箇所には小さい菱形をあしらっているようだ。
「茜にしては珍しいな、そう言う色合いを使うのって」
「そうかな?」
いつもなら茶色の地なんかの、映えない色合いを好んで使っていた茜が赤などの原色を使うのは確かに珍しい。
「これ…二葉が選んでくれた物なんだ」
「えっ?」
茜の言葉に間抜けな返事。
「別に珍しくはないよね、二葉が選定した物って」
確かにそこそこ二葉の選んだ物を持っているのは知っているし、それは別に二葉の好みを押しつけた物ではなく、茜に似合っている物を優先している事くらいは、男の俺でも分かる。
「うん。なんか、使いたくなってね」
「そうか…」
今回、茜と向かう先はただ一つ。
家から商店街の方角へ向けて歩いていると、自然とその場所に行き着き、視界に入るのは一つの場所だった。
「ここが…」
茜がぼんやりとした声でそう呟くのを聞くと、俺も僅かながらじんわりとした感触を味わう。
「二葉の事故現場…」
まだひしゃげているポールや鉄柵。雪に埋もれているだろうが、おそらく雪をどかせば下にはタイヤ痕がまだあるろうか。そして何よりも、そこが事故現場だと分かるのは、捧げられた献花やお供え物の数、だろう。
あれから、二週間と半分ほど。今でもはっきりと思い出せる。茜と一緒に買い物に来て、本屋から出たときに聞いたブレーキ音、そして少しの間を置いた後の衝突音。
あの時、もし俺があの現場に向かっていったらどうなっていただろうか。茜をあの現場に連れて行ったら、どうなっていただろうか。おそらくは、平然を保つことは出来なかっただろう。佐々木さんの様に、取り乱していただろう、と。
その現場に足を運び時間が経ってもこうして心が締め付けられるとしら、その直後に来ていたらこうして冷静な装いが出来ただろうか。それは、無理だろう。
「本当に二葉って好かれているんだよね」
茜が事故現場に捧げられた花やお供え物を見て、そう言葉にする。それは別に茜だから言う台詞ではなく、誰でもこの数を見ればそう思えるのだ。
「ざっと見ただけでも、四十以上か?」
いつから置かれているか分からないにしても、雪がまだあまり積もっていない物だけでも、片手以上は有る。つまり今日、ここに備えた人の数だろう。
「むしろ、俺たちがここに来るのが遅すぎたんだよ、な」
本当にその通りだ。事故から二十日近く。ようやく受け止められるようになるまでに要した時間だ。
もしその場に佐々木さんではなく、俺たちが居たとしたらどうなっていただろうか。これだけ時間を置いてようやく来ることが出来たこの場所に、事故直後に来たら。そう思うと、どれだけの気持ちで佐々木さんは二葉を助けようとしていたのだろうか。
想像には難しくなく、そしてとても辛い。
「直哉、私は弱いよね…」
「ああ、そうだな。でも、私も、だろ。俺だって弱い」
茜がゆっくりとその場にしゃがみ込んで、お供えされた物をゆっくりと見回している。これだけの人が悲しんで悔やんで、そして物を置いていくのだ。
ちらほらと降る雪は、絶え間なく地面を埋め続けていき俺たちが歩いてきた雪道の足跡も遠慮無く埋めていく。もちろん備えられている物にも例外ではなく、一日もすればきれいに雪で埋められてしまうだろう。
「まるで、人の記憶みたいだな」
ぼそりと茜が呟くと、両手を合わせて目をゆっくりと閉じた。
二葉を思い出そうとすると大抵は、自己紹介の時の事を思い出す。仁王立ちして自信満々の顔で話しかけてくるその姿があまりにも印象的だったから。だから、私は二葉の印象はその時のままだった。
いつだって笑って、そして頼りに出来る、そんな印象だ。
でも、あれは高校一年の夏、海に行ったときだ。直哉が居ないときに、丁度ナンパ男に絡まれたときのことだった。いつもの二葉ならこんな奴ら位、直ぐに撃退できると思っていた。でも、その時は、まるでなされるがままだった事を疑問にも思ったものだ。
直哉以外と親しくすること自体がまず無かった私は、二葉と何度もぶつかり喧嘩をして、それでも二葉は諦めなかった。
いつからか二葉を友達と思うようになり、そこから親友に変わるまではさほど時間を必要ともしなかった。二葉のぐいぐいと人の領域に入ってくる強引さと、それらを極力嫌みに感じさせない愛嬌の良さは、まさに遺憾なく発揮された。
私はそんな強さに憧れて、そうなりたい近づきたい、そう考えるようになっていった。まるで、姉の様な存在だった。
そんなとき、良子がぽつりと言った一言は印象に残った。
「二葉は、強くなんて無いんですよ」
私何かより二葉をよく知っている良子はそう言葉にした。
そしてそれから間もなく、事故による、まさかの別れで、その答えを探ることは永遠に出来なくなってしまった。
まだ、二葉と一緒に遊びたかったし、言葉を交えたかった。不安になりながらも直哉を取り合うのもある意味では、そう言うコミュニケーションだったと思える。
少し高めの張りがある声や、その声にぴたりとイメージが合うポニーテール、そしてそれらをまとめるような行動力。私とは有る意味で反対側に存在するから、私は羨ましいと思ったのかも知れない。
模倣した私と、自分を確立した二葉。人の真似をすることで好かれようとした私に対して、ありのままの自分を全力でぶつけた二葉。この差は、おそらく埋めようがない物だ。
でも…埋められなくても、近づくことは出来たんだと思う。その時間はもう存在せず、平行線が永遠と続いていくのだとも。自信が無いのは分かっている。夢ですら二葉から怒られたんだから、もし生きていたとしたら同じような事を言われたのだろう。
でもね、二葉。私、自分なりにどうしたらいいか、考えてみようと思う。もしその答えが見つかったら、二葉に報告しようと思う。その前に、そちら側にいっちゃうかも知れないけどね。
「もう…大丈夫かな?」
そんな優しげな声が聞こえる。もっと長い間付き合っていきたかった友達の声。もしかしたら有ったかも知れないもう一つの可能性に生きた私の声。
「うん…大丈夫、だよ」
問いかけには、そう言葉を返すことが出来た。
「お前は、心配じゃないのか?」
義明がそう小さく呟いたのを聞いた。
「はっ?」
「なんでお前はそこまで平然としていられるんだ?」
平然としている気は更々無いのだが。
「俺は、心配で心配で気が狂いそうだって言うのに…」
茜を一瞥して次の言葉を選んでいる様な義明。
「二葉の事だって忘れた訳じゃないだろ。あの時も、お前は何事も無いようにしていたよな」
確かに俺は、二葉が入ったあの車を見送るときですらぼんやりとしていた。それは実感が湧かなかっただけだったし、後々茜と一緒に泣いたのはまだ記憶にも新しい。
「違う。俺は…」
「じゃあ、何でだ? こう言う時くらい感情を出しても良いんじゃないのか?」
感情をむき出しにするのは本当に怖いことだ。
「誰も、お前がこの状況で泣いたり心配したりするのを見たところで責めもしないだろう?」
そう、誰も俺を責めることは無いだろう。でも、誰が今の状況を引き起こしているかを考えると、感情を表に出すことが出来ない。
「苦しいんじゃないのか? 辛いんじゃないのか?」
義明が堪えるように声を抑えている。感情が昂ぶらないように必死に耐えているようで。
「お前は…月詩さんが好きなんだろう?」
真っ直ぐ俺と視線がぶつかった義明の顔は、本当の真顔。いつもおちゃらけているようなこいつが、真顔でそう聞いてくる。
「俺は、茜の事が好きだよ」
だから俺も今、はっきりしている事を義明に言葉で返した。
「じゃあ、感情くらい素直になったらどうなんだよ。俺だけじゃない。佐々木さんだってお前のことを心配していたよ」
「佐々木さんが?」
「ああ。疲れた顔をしているのに、なんで本音を聞かせてくれないのかって。月詩さんの容態も気になるけど、それ以上にお前の事を心配していたぞ」
俺の事を心配する、か…
「なぁ…なんで俺なんかを心配するんだろうな?」
ぽつりと口に出したその言葉は誰に向けてなのか。義明に向けているのか、ここにいない佐々木さんに向けてなのかは俺自身にもはっきりとは解らない。
「何?」
義明が言葉を返してくる。
「佐々木さんが茜を心配するのはよく分かるけど…俺を心配してどうするんだろうなって」
今でさえ、表向きは原因不明の症状で苦しんでいる茜の心配なら十分に納得できるが、俺の心配をする理由がよく分からないでいた。
「おいおい、直哉。それは冗談で言っているのか?」
「なんでだよ。俺は至って問題ないだろ?」
なんて言い返せばいいのか悩んでいるらしく、何度か口を開け閉めしているが、落ち着こうとしたのか大きく溜息を吐いた。
「どこがだよ」
頭を抱えるように項垂れた義明は、頭をガリガリと掻くと顔を上げて俺をじっと睨む。
「可笑しいと思っていないのはお前だけだよ、直哉」
呼吸を一つ挟んで言葉を続けた。
「お前、佐々木さんが月詩さん以外はどうなっても良いって思ってるのか? それとも、お前は月詩さんの隣に居る木偶の坊とでも思われているってか?」
「そうじゃない」
「でも、直哉が言うのはそれと同じ事だよ。月詩さんが何とかなれば、後は知らないって普通考えるのか?」
言葉を返せずにただ口を閉じている。
「直哉、お前。佐々木さんを冷たい人だとは思わないだろ」
縦に首を振ることにより意思表示をする。
「俺なんかよりよっぽど事情に詳しいだろう佐々木さんが、心配しないわけがないだろうが」
「でも、茜と俺の状態を比べる方が可笑しいだろう?」
言葉を返したら、また頭を抱える。
「問題有り。問題有りだよ、直哉」
上手く義明との会話がかみ合っていない様な気がする。それとも、俺が義明の言いたいことを読み切れていないのか?
「お前、心配するのに上下の区別も必要か? 心配するって言うのは、順序をつける必要があるのか?」
それは無い。でも、俺は心配されるような状態ではないと思うのだが。
「直哉、やっぱりお前も疲れてるんだ。少し休め、な?」
「……俺は、大丈夫だよ。疲れてなんていない」
体の疲れは解っている。慣れない状態で体が疲弊するのは仕方ないことだけど、まだ十分に許容の範囲内だ。
「直哉お前、何をそんなに思い詰めているんだ…違うな」
まるで品定めをするような仕草と目線で俺を見る義明は、ぶつぶつと小さく呟いている。それが大体十秒程経った頃だろうか。
「何を、隠しているんだ、お前。なんか自棄になっているように感じるんだが?」
隠していると言う義明の言葉に体が一瞬だけ反応した。
「…で、どうなんだ?」
一瞬の反応を見逃さなかった義明が更に問い詰めてくる。もっとも、事実を話したところで理解は得られないだろうし、場合によっては茜にも迷惑をかけることになる。それだけは避けてしまいたい。
「なぁ、義明」
「なんだよ?」
茜の笑顔が頭に浮かんで、イメージが固定する前に消えていった。
「もし、俺と茜の立場が逆になったら良かったのかな?」
茜が俺の力を持っていて、俺は茜からその力のせいで目の前のベッドに眠っている。そんな仮定の話だ。
「それこそ、どういう意味だ?」
眠る茜の顔を見て、先程浮かんだ茜の笑顔を再度イメージする。
「言葉通りだよ。そうすれば、少しはまともになるのかなって」
茜のように心配してくれる人が少ない俺だから言える言葉。
椅子から腰を浮かしてゆっくりと歩き出した義明。
「俺って、ほら、基本的に茜やお前、二葉や佐々木さん以外と親しくないからさ」
もっとも、そうなった場合、茜や義明達には心配をかけてしまうのかも知れない。
「もし、そうだったら…義明に茜を任せても良いかなって思ってるんだがな」
隣に歩いてきた義明がおもむろに俺の襟を掴むとそのまま急に持ち上げられた。驚く程の力だった。
「直哉、お前人を馬鹿にすんのも大概にしておけよ!」
いきなりの怒声と立ち上がった際に足に引っ掛かった椅子が倒れて病室に音が一瞬飽和した。