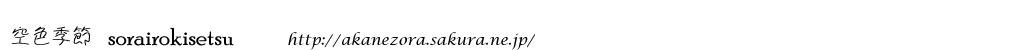
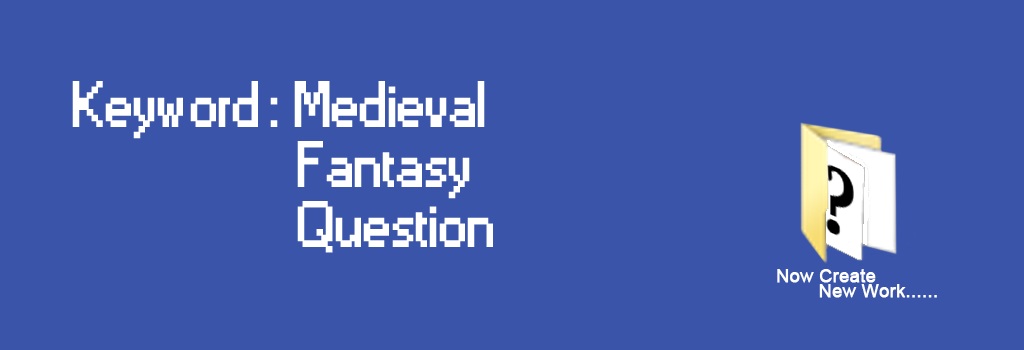

熱い吐息がかかりそうな距離、少し潤む瞳に目端には涙。短くなった髪の毛がベッドに申し訳ない程度に広がっている。
茜。見慣れた茜じゃなく、ちょっと違う茜の顔と視線を真正面から受け止めて返している距離は、十センチも無いだろう。
力の差は男女の差であり、運動が得意な茜でも華奢な身体で出せる力は決まっているのだからこうして容易く組み伏せる事が出来るのだ。
少し驚いた顔をしていた茜。でも直ぐに元通りの表情に戻っていくと俺は痛む心を誤魔化すように自分へ言い訳をするんだ。
でも、茜が俺に向ける視線の中にある感情は、怒り。単純な怒りではなく恨みや妬み、それらをごちゃ混ぜにした感情が今、何のフィルターを通すことなく向けられていた。
なんで、こうなったんだっけ。
教室の空気が暖かいのは気温の話だけだ。
そこにある雰囲気はただ氷のように固まり、何も動かず何も話せずただ冷え固まっているだけだった。
「どうして…」
誰かそう呟いたのが教室の静かな空気に波紋を立てる。誰が言ったのかが重要ではなく、それはこの教室にいる全ての人が聞きたい質問であり、誰が出しても可笑しくない質問だからだ。
どうして?
その質問だけがクラス担任である、おがTから出た言葉に対しての疑問、それ以外は浮かびようもなかった。
言葉にすることすら、阻まれるような雰囲気にそれでも言葉を続けるおがTも言葉をどう出して良いか迷っているようにも感じる。
「先日、交通事故に遭い病院へ搬送して、先日の未明に息を引き取ったと、家族の方から連絡が入りました」
冗談だとしたら、質が悪いことこの上ないだろう。ただ、その言葉には嘘や偽り、ましてや人を騙そうとする響きはなく、むしろ無理矢理でも信じろと言わんばかりの強制力すら感じてしまう。
「先生も今日の朝、連絡が入ってな。信じられない…そう思った」
沈む声に、教室の明るさも落ち込んだように感じた。窓から入る冬の陽射しは、暖かいはずなのに一向に心地良いという感情は湧かず、両足が泥沼に入ってしまったような重さが足下からじわりじわりと浸食してきた。
「なんでも、バイト中の買い出しで外に出ており、その戻りで交通事故に遭ってしまったとのことだ。道路の凍結や雪の影響だろうと警察が調査を続けてくれているそうだ」
誰がそんなことを考えられただろうか。つい数日前には一緒に文化祭お疲れ様と言い合って俺の家で騒いでいた。家に忘れていった髪留め用のゴムも返していないのに。
俺からすれば、憧れるような強さを持つ二葉、茜からすれば、初めて出来た親友という存在。
笑って別れたあの大きめの交差点。今では数が少なくなった電話ボックスが置いてある交差点。軍隊の真似をして敬礼をした二葉の姿が今でも鮮明に思い出せる。
「ひとまず、気乗りはしないだろうが今日は授業を続ける」
そこまで言っておがTがホームルームの時間を確認するために腕時計をみようとする仕草の時、隣から声が聞こえた。
「うそ……」
「んっ?」
小さな呟きだが、教室の静かな雰囲気の中では聞き取ること位難しいことではなかった。
「うそよ……」
「茜?」
茜がうなだれながらそう呟いている。髪に隠れた表情は伺えずただ茜の声がそこから漏れてくるだけだった。
「だって…あの時、別れるとき…またねって、二葉、言ったよ?」
初めて茜がこちらに視線を向けた。
誰だ、そう思った。思えてしまった。
「また、休み明け、学校でって、言ったんだよ、二葉」
「茜、落ち着け」
教室の中では他にも悲しみを堪えるような小さなすすり泣きいが聞こえてくる。それは他の女子がそうしているのだろう。ただ、声を出しているのは、茜とそれに応える俺だけだった。
「おがTっ! 嘘だよねっ」
茜がおがTの方向へ視線を向けた。だが、それにはどう答えて良いのか解らず苦い顔をして、言葉を返すことはない。
「だってっ…だって、あの時、二葉は今日会うって自分から言ったんだよっ」
茜の声に混じるのは悲しさだけではない。
この言葉の中に含まれている感情や想いは、五年前の自分自身を思い出すようで心がとても苦しくなってくる。
「ねぇ、直ちゃん、嘘だよねっ」
「茜、落ち着け」
俺は、俺自身自分に驚いていたんだ。
「なんでよっ、そんな風に落ち着いてなんかいられないよっ」
なんでこんなに二葉の訃報を聞いても心が揺れないんだろうか。
茜の声を誰も咎めることは出来ず止めることも出来ず、ましてや落ち着かせようとしても無意味なのはわかりきっていた。
「お願いだから…落ち着いてくれ」
「なんで、なんでなのよっ!」
声が震えた。感情が心というものを動かし、感情という力を働かせ茜の涙という形に変換していった。
茜の悲痛な声に感化されるように教室中の空気が一気に悲しみの方へ流されて、埋め尽くされた。
そんな中、俺はなんで気持ちを揺さぶられないのだろうかそれが気になっていた。
茜の意識が俺に向いたのを感じて、それでまた小さく気持ちが痛んだのを感じた。
「おはよう。待ったかな?」
「あっ…いえ、今来たところですよ」
嘘を言っている位は直ぐに解った。雑踏に紛れそうな程の寂しそうな顔で、時計を気にしていた彼女の姿をちらりと見えてしまったからだ。
「そっか。その格好だとちょっと寒くない? 大丈夫?」
「そうですねぇ…」
ライトグリーンのワンピースに白いロングスカート。まさに彼女のイメージ通りの格好で、俺は遠目に見ても解ったくらいだ。
そしてまた見失わないように、雑踏に紛れないように左手をだしたのだ。すると、ちょっとだけ間を置いて彼女は手を差し出して、そっと俺の手を握った。
「手を繋ぐだけでも暖かいね」
彼女の嬉しそうな声を聞いてこちらまで嬉しくなりそうな気持ちを、軽く手を握るという行為で返してあげる。
「まだ、五月だと肌寒く感じますね」
「そうだね。でも暖かい日もあるから」
「こうして、居元君と手を繋ぐと尚更そう感じちゃうな」
ここ最近の気温はずっと暖かかったのに、五月に入ってから一気に落ち込み始めて、今では最高気温との差がかなり大きくなっている。そんな中でも折角のゴールデンウィークなんだから、寒いくらいは我慢をする。
「それにしても…良いんですか?」
「何が?」
彼女の質問が何を指していることなのかが解らない。それに前後の脈絡が見あたらない。
「その…折角のゴールデンウィークなのに私と一緒に居ても?」
「全然問題ないよ」
「それに、その…月詩さんも誘った方が良いのかなって」
なんで茜が出てくるのだろうか。
「それなりに気にかけていたようですし」
確かに、茜に彼女のことが好きだって事を言ったら随分と俺に質問やら何やらをしてきていたっけ。
「まあ、茜とは古い付き合いって言うか。友達だけどね」
色々有ったのは言うまでもないけど、友達という関係には間違いはないはずだ。
「友達、ですか。なるほど」
何になるほどなのか少し疑問。
「それで、何処に行こうかな…ちょっとまだ考えていないんだ」
「あっ、それでしたら、本屋さんに行っても良いですか?」
「本屋?」
商店街に在る本屋と言えば数店舗在るが、何処だろうか。
「あの広場より東側にあるちょっと大きい本屋の方なんです」
茜と何回か行ったことがある。多少広いフロアでそれ相応の本が置いてあると言うことで、茜が何冊か哲学書を買っている。
「私、その恋愛小説って好きなんですよ。ライトノベルとか。そのファンタジー物とかも呼んだりします」
こちらから何も言わなくても、言葉を繋いでいく彼女に俺はちょっとだけ驚いていた。少し物静かな彼女がココまで言葉を繋げていることが、珍しく感じた、とは言えあまり話したことが無い俺だからかも知れないが。
「その、なんていうか憧れるんですよ。ライトノベルの世界って」
「そうなんだ。俺はあまり読まないから解らないけど…」
「あっ…そのすいません。一人で盛り上がっているようで」
途端に声のトーンが小さくなるのを聞いて、今の一言は失敗だったかなと心で舌打ちをすると、直ぐに首を横に振った。
「いや、そう言う意味じゃなくて。今度俺にも本のお奨めとかを紹介して欲しいかなって」
場を繋ぐためとか、話を合わせるためにそう言ったわけではなく、単にそこまで彼女が熱く話をするから気になった。
「あっ、そうですかっ、よかったー。じゃあ、今から本の紹介をしますよ。私が読んでいる本だけですけど、きっと居元君も気に入ると思うな」
そう言うと、笑う彼女のおさげが嬉しそうに左右に揺れた。