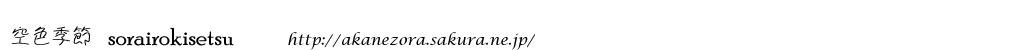
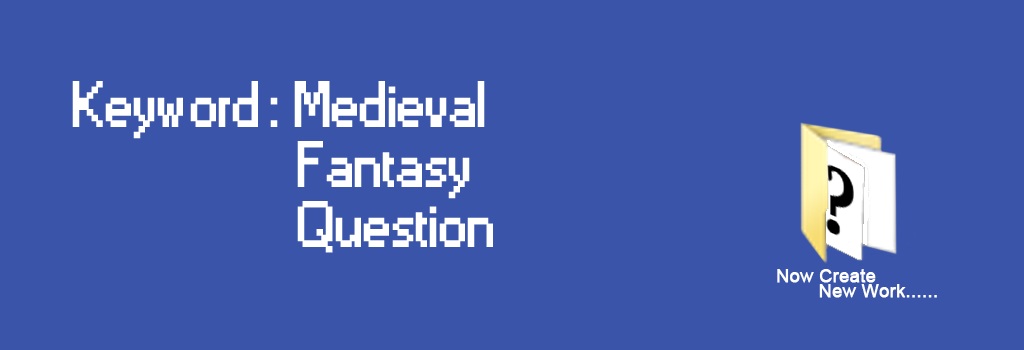

肌に当たる水滴は一度は跳ねて、体のラインに沿って流れていき最後は床のタイルに到達する。全身に当たるお湯の感触、背中や肩に濡れた髪が当たる感触、両方とも私は好き。昔は鬱陶しかったこの長い髪も、慣れてみれば意外と悪くはないものだと思えた。
あの五月の一件からもう三年半、随分と伸ばしたと思うこの髪も背中を隠す程まで伸びた。今では、二葉の言葉じゃ無いけど自慢の髪だ。
「茜って、髪、すんごい綺麗だよね」と言い、すぐに髪の毛を弄りたがる二葉やそれを助長するように良子も手伝うのだ。三つ編み、ポニーテール、ツインテール等々、大きく分類しても多数ある上に、創作の髪型まで試される事もある。こうして指折り数えてみると、優に二十は越える回数を弄られているのだと思い出せる。
ツインテールの時は、どうしようかと思ったものだ。クラスの人だけじゃなく、学校の人から珍しがられたから、恥ずかしくて顔を真っ赤にしていた記憶がある、というか、直ちゃんにそう言われた。
「顔が真っ赤だぞ」って、苦笑しながら私に言った直ちゃん、それでも髪型を戻すように二葉達に言わなかったのは、故意なのか気になるところだ。
湯気が立ち上り、浴室の中を白く染めている。脳裏の白紙に記憶という風景を上らせて描いては、徐々に薄れていきまた白紙になる。繰り返し繰り返し何度もそうやって居ると、たまにだけど妙に胸がすっきりとすることがある。
使い慣れたシャンプーにリンス、トリートメント。それらを見つめて自分の髪の毛を一房、つかんでみた。
浴室内と同じく、頭の中を白く染めていく。浮かぶ記憶は、中学校二年のゴールデンウィーク。少しばかりいつもより晴れている、ただそんなありきたりの一日のはずだった。
随分と長い間、シャワーに入っていたみたい。髪を拭きながらもドライヤーのスイッチを入れると同時に温風が出る。ドライヤーの風に逆らおうともしない髪。水気で濡れているものの風の力にゆらゆらと揺れては徐々に余計な水分を失いつつある。丹念に優しく、タオルで水気を飛ばした髪は何時もある癖気を無くしてくれる、一時的なものだけど。どんなに直してもすぐに現れるこれは、いわば私の天敵でもあるのだ。
「良子くらいまで…髪、切っちゃおうかな?」
今より二十センチメートルほど切ってしまえば、お手入れも大分楽になってしまうんだけど。
そうも行かない理由くらいはあるのだ。もし無かったら、本当に髪の毛を切っていたのかも知れない。髪の毛は命だと言い切る人もいるくらいに大事な存在だと、昔は思いもしなかったのに今となっては言うまでもないほどだ。
ショートにしていた頃からある癖気。長くすることで消えるのではと淡い期待は時間の進行と髪の伸び具合とで徐々に薄れていき、最後には諦めにもなる。未だに、直らないかなと思うことはあるのだけど。
パジャマに袖を通して部屋に戻る頃には、夜も更け冷え込みも厳しくなってくる。その対策としてタイマーをセットしたストーブの恩恵にあやかる事が出来る。
ふ、とそこまでして携帯のランプが点滅しているのに気がついた。あの色は、着信を示す色。
「誰、からだろう?」
真っ先に浮かんだのは二葉だった。それなりに心配しているからかな。二葉に昔、彼氏が居たことは思いの外、驚いてしまった。
「まあ、恋愛の先輩だからかな…」
折りたたまれた携帯を開き、ボタンを押して画面に映された名前。
「えっ…直、ちゃん…」
「えっ…誰?」
私の声に反応するように、直ちゃんが歩く姿勢から完全に止まる姿勢へと変わった。相手の顔を見ようと半歩だけ横にずれると、ようやく見ることが出来た。
黒いニット帽を目深に被って大きめのコートを羽織っている男と、パーカーとジーンズの男の二名。共に記憶にない顔だった。路地裏の十字路を少し過ぎた辺りで止まっている私たちの、進行方向から歩いてきたらしい二人組は、道を譲る気はないように見える。
「悪いけど、そこ通りたいんだけど」
直ちゃんの声にもほぼ無反応。黙って立っているだけなのだが、直ちゃんはなにやら険しい声、顔つき。
「えっ…?」
十字路の左右からさらに男が一人ずつ。似たような格好で、大柄な男と、ピアスやらチェーンやらの貴金属をこれでもかとつけている男の二人。前と後ろ、共に離れていても四メートルと行ったところか。それも徐々に近寄られているのだが。
「ねぇねぇ、そこの彼氏」
ニット帽の男がリーダー格だと判断。初めて掛けられた声は友好的とは言えず、馬鹿にされている、むしろ敵対されていると捉えてもいいような話し方だった。
「お金とか持ってない? ちょっと貧乏な俺たちに恵んでくれよ」
右の手のひらを上に頂戴のジェスチャー。明らかに恐喝の類だろうが、狙っていたように路地裏で囲まれてしまったようだけど。
「ねぇねぇ、それに隣の彼女?」
パーカーの男が私を指さしている。直ちゃんも尻目にだけ私を見て、極力注意は周囲へ向けているようだけど。
「俺の事、覚えてる? 覚えていないでしょ、その顔じゃあ」
「茜、知り合いか?」
直ちゃんの言葉に、私は言葉ではなく首を左右に振って否定すると、パーカーの男は首を竦めて「これだもん」と馬鹿げたように声を上げた。
「ははは、お前、ばっかじゃねぇ。覚えているわけねぇだろ」
「うっせぇ。酷いじゃないか、アカネちゃん」
なんで、この男が私の名前を知っているのか、まったく解らなかった。直ちゃんと春日君、マスター以外基本的に男性と行動しないため特に気になってしまった。
「ほら、一ヶ月くらい前、そこの交差点で待っていた君をさ、ナンパしていた男」
ナンパ、交差点、一ヶ月前……あっ。
「二葉に殴られたやつ…」
へらへらした顔でしつこくナンパしてきたあげく、二葉から綺麗に顔面へストレートを貰ったあげく、その場に放置させられた男。
「そ。さっき事故があった交差点でアカネちゃんをナンパした男ですよ。思い出してくれた?」
事故があったって、あの交差点だったんだ…確かに車通りは多いけど。
「もう一人、可愛い子居たよね。ポニーテールの。痛かったんだよね、もう晴れちゃってさ」
「自業自得じゃない?」
ナンパはやり過ぎと思うくらいじゃなきゃ撃退できないと二葉も言っていたから別に妥当だと思うけど。
「悪いけど、金は無いから、通してくれ。これで用はないだろ。茜行くぞ」
直ちゃんが私の手を引っ張って歩き出そうとすると、パーカーの男が両手を軽く広げて通せんぼの格好をとった。
「おーっと、おーっと。んじゃ、野郎にはもう用事はないから、アカネちゃんだけ残ってよ」
「悪いけど、俺の連れなんでそれは無理な話なんだよ」
埒があかないと直ちゃんも思っているだろう。ああ言えばこう言い返す、と時間の無駄だと言うことも。せめて、十字路だったら、上手く行けば逃げられたかも知れないけど、十字路は後ろの不良達よりさらに数メートル後ろだ。
「アカネちゃんはどうよ。一緒に遊ばね?」
「いやよ」
はっきりと否定の声が出たのには自分なりに褒めてやりたい所だ。何回かこういう事を経験するとそれなりの対応が出来るようになるのは、嬉しいことなのか嬉しくないことなのか。
「というわけで、俺等は帰るから、どけ」
直ちゃんの握っている力が少し強まるのを感じて、少し苛立っているのだと言うことを察知することが出来た。
「あっそ。おとなしくしておけばいいのにね」
ニット帽の男が軽くため息をついて、わざとらしく悩むポーズをとると、少しの沈黙が路地裏を一気に制した。室外機の音が耳に良く響いてうるさくも感じた。
「じゃあ、さ」
「むりやりだな」
「だな」の辺りで、ふっと風を感じたと思いきや、次の瞬間、目に映ったのは直ちゃんの後頭部へ向けて降り下ろされている、金属質の固そうな棒だった。
「直ちゃんっ!」
路地裏に私の声が響いた。同時に、鈍い音が私の声と一緒に発せられたのを、私は確かに聞いて、そして忘れない。